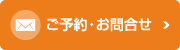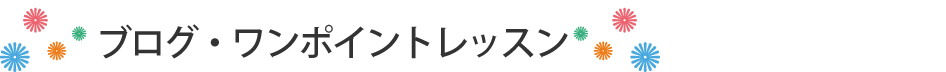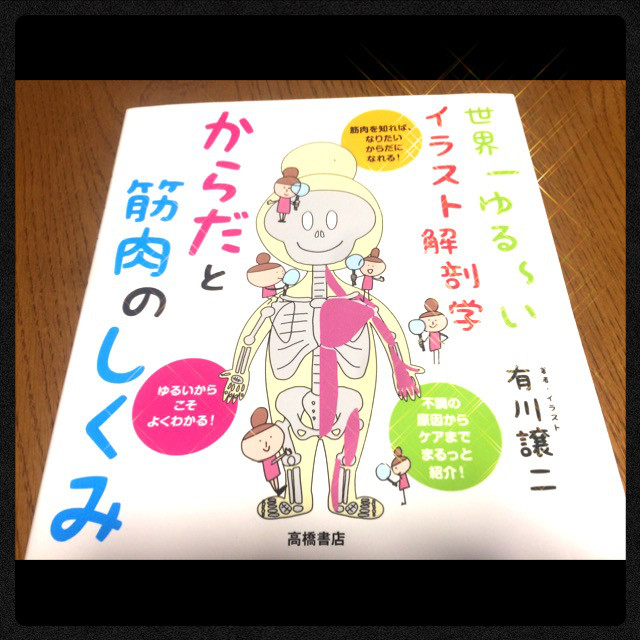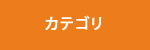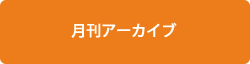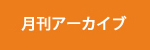ブログ・ワンポイントレッスン
ブログ
「きのうかいぼうがく」を学ぶ
最近面白い本を見つけました。
こんばんは。
スポーツひろばの今村こころです。
今、横浜教室で1番人気の本となっております。
この本は、子どもたち・・・だけでなく、レッスン中ふと見るとお母さん、お父さんが手に取っている場面が1番多いですね。
肩こりとか膝の痛み・・・とか大人が直面するお悩み解決にも触れてあるからかもしれません。
跳び箱や鉄棒・・・よりは自分の身に降りかかるかもしれないこととして、感じることができるからかもしれませんね。
話を変えて、
体の専門家が必ず通る道・・・
からだのしくみを学ぶ学問に
「機能解剖学」
というものがあります。
「解剖学」
部分を学び、ミクロ的に一つずつの組織を見る
・・・・ことは大事ですが、実際身体は部分部分が組織として繋がり、かかわりあって動いている1つの連続体です。
「機能」とは全体を構成する個々の部分が果たしている固有の役割のこと
問題を解決したり、目標を達成するためには、
ミクロだけでなくマクロに連続体として捉える必要があります。
全ての組織を連続体として捉え、各々の機能を解剖しながら理解する学問が、
「機能解剖学」なのです。
これは運動指導をする上でも同じ考え方・・・と言いたいですが、
人間の頭を通して行うものなので、学問として確立されているもののように、
指導法はかっちりとは行きません。
体の動かし方を学び身につける上で1番大切だと私が考えていることは
【イメージすること】
正確には
【イメージできること】
よく指導の上で
「イメージしろ!」
「意識しろ!」
という言葉は使われますが、
これってとっても抽象的で難しいことだと感じています。
目的となる運動や動作につなげるために、人それぞれが頭の中で思い描くイメージは違うもので、正解はまずありません。
つまり、本人は意識しているけれど、目標とする動きや目に見える結果につながらなければ、それは意識しているつもりであって、頭の中の努力や想いや頑張りは目で見ることができません。
結果、
「もっとイメージしろ!」
「もっと意識しろ!」
など、もっととか、しっかりとかいう形容詞が付き、具体的な解決には一向に近づかず、本人は苦しむか萎えるか自信を無くす・・・ということにもなりかねません。
最終的にはイメージ、ですが、学習者にはまらないのであれば、指導者としては引き出しは沢山持っていたい。
それは根性だけにたよらない具体的なものです。
ということで、
体をこのように動かすという動作そのものは客観的で確固たるもの!
これらを踏まえて表現を考える上では専門家としてはマストだと考えております。
『部位や動きを伝える』
=(イコール)
『イメージしやすい表現に翻訳する』
ということをが、最も日々のレッスンで試行錯誤していることです。
そんなこんなで、
「いいものないかなあ~」
と本屋をうろうろしていたときに見つけたのがこの本でした。
とにかくざっくりと、体の骨・筋肉・関節など・・・・
からだの部位(解剖学)やその動き(機能)がわかりやすいイメージで示されているのです。
言葉だけではなく、目で視覚的に見たほうがわかりやすい!
ということで時には紙に書いたりして伝えるときもあるのですが、
私の画力では体を的確な図で示すのは限界が・・・・ということで、
この本の関係する部分を見せながらレッスンをすることもあります。
子ども「へー、体ってこんなふうになってるんだ。」
食い入るように見入る子がほとんどです。
運動をしている自分(の体)に興味が沸く・・・ということも、
運動って「楽しい・面白い」の1歩になるかもしれません。
「機能解剖学」といえば難し気に見えますが、
この本は老若男女問わず、誰でも学びやすい導入として、
助けてくれる1冊です。
ひとまず、導入・・・始まりがなければ、経過も終わりもないですからね。
自分の体とのお付き合いは一生もの!
「きのうかいぼうがく」
是非、学んでみてはいかがでしょうか?
P.S.
この本、手に取ったときに裏を見て驚き!
なんと私の大学時代の親友が作った本でした(編集者として)!
仕事は違っても、何かを形になるものを作り、それが誰かの役に立つ、という形で繋がっていくことはすごいなあと感じたりもしています。まさに連続体!